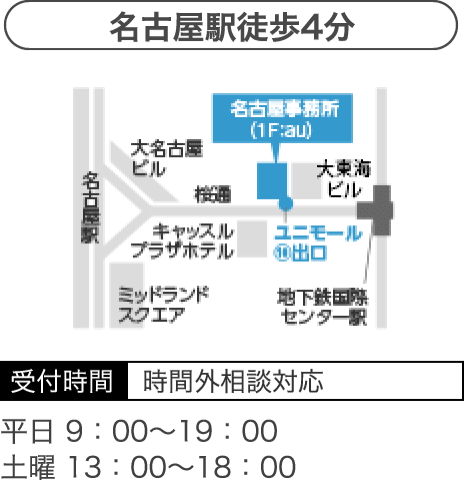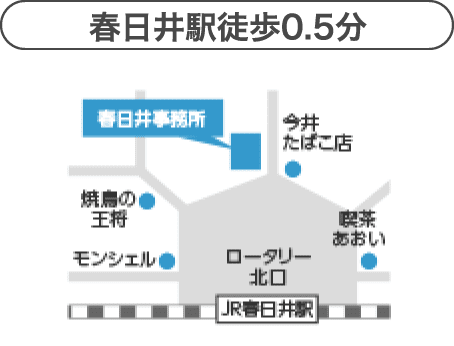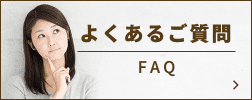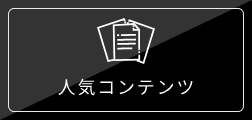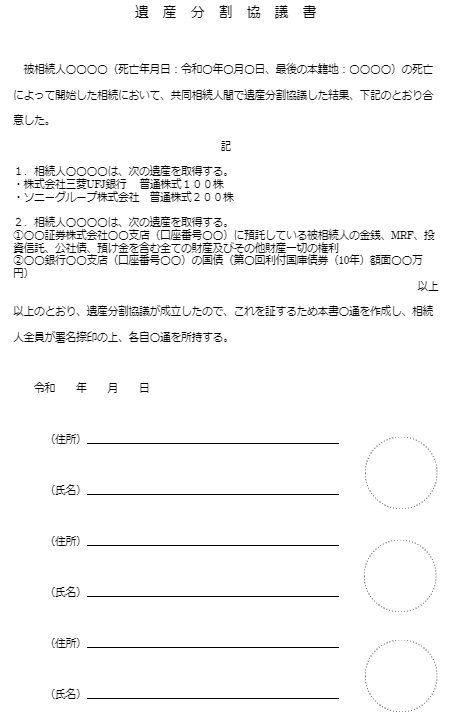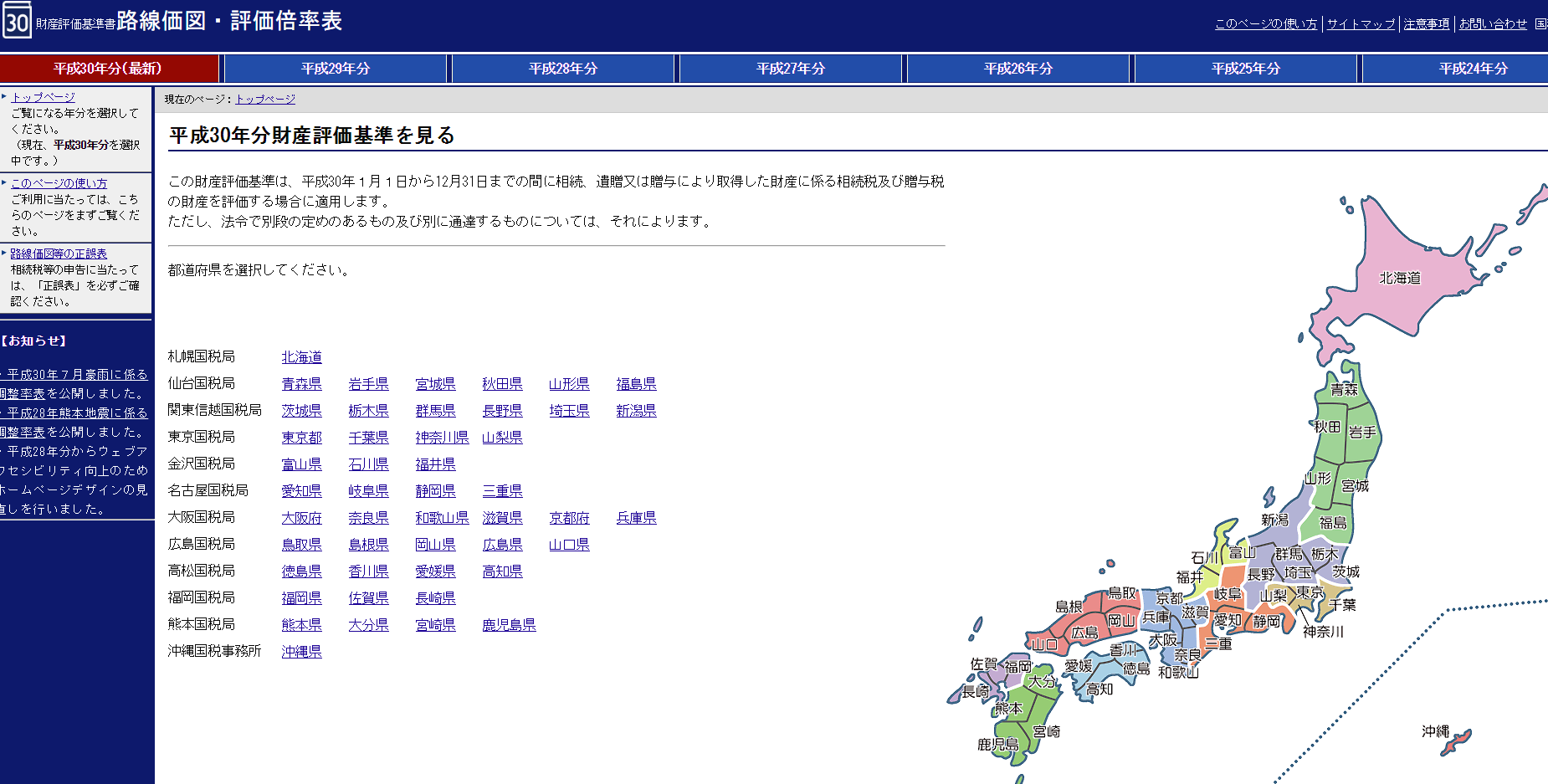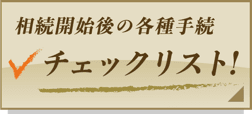遺言書を有効に作成するためには、「遺言能力(いごんのうりょく)」が必要です。遺言能力とは、遺言の意味や遺言の結果どのような法律効果が生じるかを理解できるだけの能力のことをいいます。そして遺言能力がない者が行った遺言は、無効と解されます。公正証書遺言の場合は、公証人が遺言能力を確認するため、遺言能力の有無が争われることはほとんどないと考えられますが、自筆証書遺言の場合は、公証人の確認がないため、後日相続人間で紛争となる可能性があります。
遺言能力の有無は、遺言書作成当時の認知症の程度や状況にもよるため、一概には明らかでないことも多いと思われます。そのような場合でも、遺言の効力に疑義があり、その有効性を争いたい場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停のなかで遺言が無効であることを主張立証する方法が考えられます。また、遺言によって利益を受ける相続人が遺言の有効性を主張し、全く譲歩しないような場合には、地方裁判所に対して遺言無効確認の訴えを提起する方法が考えられます。
1.遺言の有効性
遺言が有効であるためには、①遺言が法律の定める要件にしたがって作成されていること、②遺言書作成時に遺言者に遺言能力があったこと、が必要です。
①の要件が問題となるのは、主に自筆証書遺言の場合です。自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないとされています(民法968条)。
②の遺言能力とは、遺言書作成時において、遺言の意味や遺言の結果どのような法律効果が生じるのかを理解できるだけの能力のことをいいます。未成年者や成年被後見人、認知症の方が遺言を作成する場合等に問題となります。
1-1.未成年者
未成年者は、満15歳に達していれば、遺言をすることができます(民法961条)。未成年者が法律行為をするには、原則として親権者の同意が必要ですが、遺言をする場合は親権者の同意がなくても作成することができます。ただし、満15歳以上の未成年者であっても、そもそも遺言能力がない場合は遺言を作成することはできません。
1-2.成年被後見人
成年被後見人が遺言をするには、事理を弁識する能力を一時回復した時において、医師二人以上の立会いのもと行う必要があります(民法973条)。成年被後見人は、常に判断能力がない状態であるとされていますが、一時的に能力を回復する可能性も考えられるため、上記のような条件で遺言をすることができます。
1-3.認知症の方(又は疑いのある方)
認知症の診断を受けたからといって、必ずしも遺言能力が否定されるわけではありません。あくまで遺言作成時において遺言能力があったかどうかによって、遺言の有効性が判断されることになります。
2.遺言能力の判断基準
遺言能力があるかどうかは、概ね以下の要素を総合的に考慮して判断されています。
①医学的見地(診断書・鑑定書、医療・看護記録)
②遺言内容の複雑性、遺言の形式(運筆、財産額、自筆証書遺言か公正証書遺言か等)
③本人の状況と周りの者との関係(本人の性質、生前の意思、周りの状況・介護の利用)
また、複雑な内容の遺言よりも、シンプルな遺言の方が一般的に理解しやすいと考えられることから、遺言内容がどの程度複雑であるかも考慮されます。
3.遺言の有効性を争う方法
被相続人が、認知症等により遺言の内容を十分理解せずに遺言書を作成していた場合には、診断書や医療・看護記録、介護施設の日報などを取得の上、遺産分割調停や遺言無効確認の訴えの中で、遺言書作成当時に遺言能力がなかったことを立証していくことになります。
参考条文
民法
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。