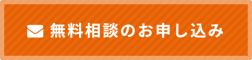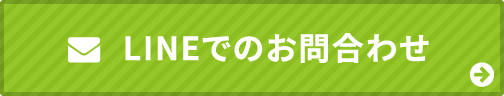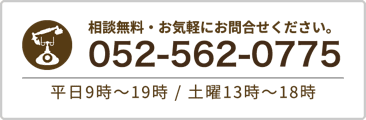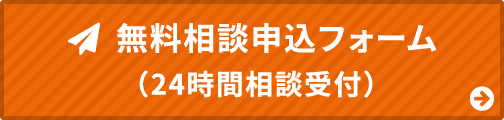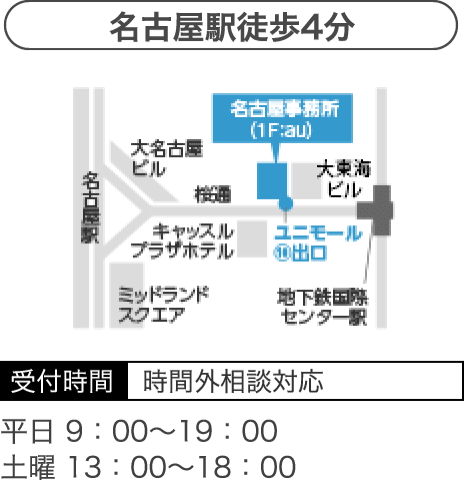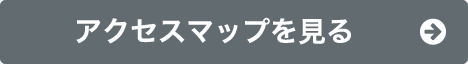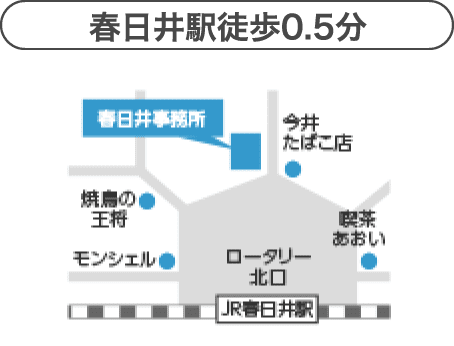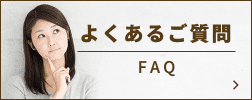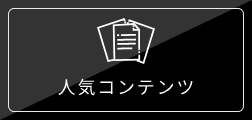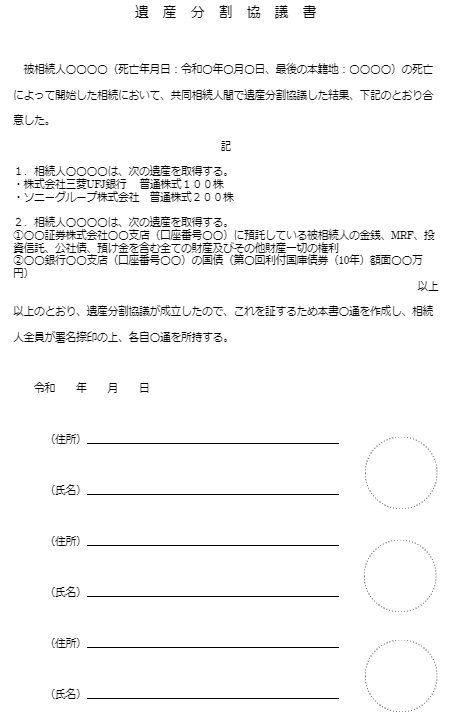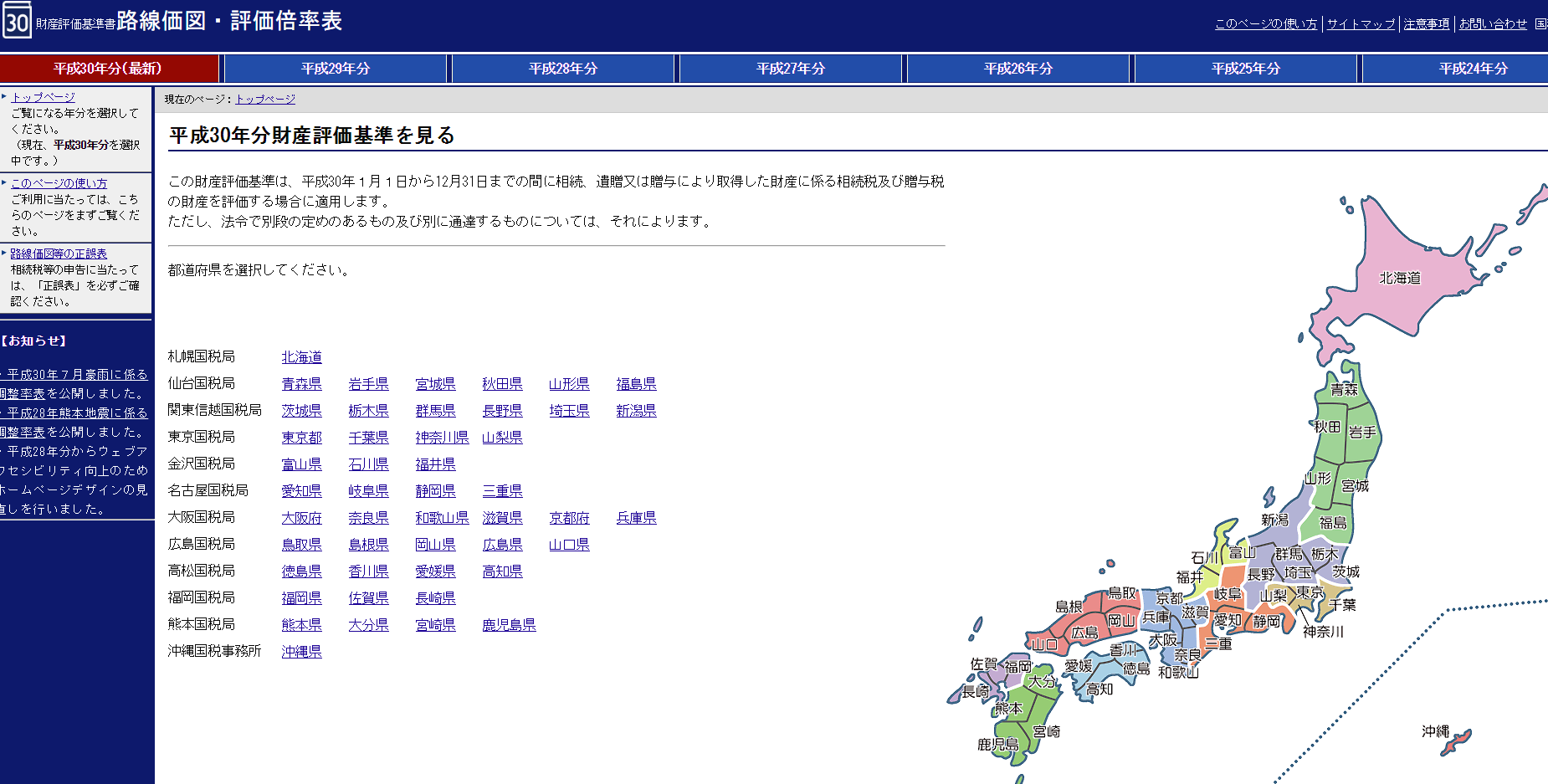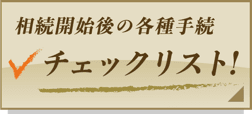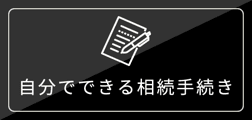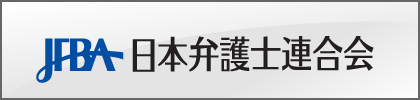遺言書が2通(複数)ある場合について、民法は、「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」と規定しています(民法1023条1項)。
したがって、2通の遺言書の内容が抵触する場合、作成日の新しい遺言が有効となります。もっとも、これは、「抵触する部分について」の規定であるため、抵触しない部分については、前の遺言が有効ということになります。
1.遺言書が複数ある場合の民法の規定
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます(民法1022条)。
公正証書で遺言を作成し、受遺者に遺言書正本を預けていたような場合でも、遺言者は、遺言の方式によって、いつでもこれを撤回することができます。
そして遺言を撤回する場合、遺言の方式による必要があります。
例えば、公正証書遺言を作成した後に、前の遺言を撤回する場合、別の自筆証書遺言や公正証書遺言等によって撤回する必要があります。
もっとも、後の遺言によって明示的に撤回する旨の記載がなくとも、次のような場合、遺言が撤回されたものと評価されます(撤回の擬制)。
- ①前後の遺言内容が抵触する場合
- ②遺言内容と遺言者の生前処分が抵触する場合
- ③遺言者が故意に遺言書又は遺贈の目的物を破棄した場合
2.抵触する複数の遺言がある場合の取扱い
そして、遺言書が複数ある場合について、民法は、「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」と規定しています(民法1023条1項)。
したがって、2通の遺言書の内容が抵触する場合、抵触する部分については、作成日の新しい遺言が有効となります。
もっとも、これは、「抵触する部分について」の規定であるため、抵触しない部分については、前の遺言が有効ということになります。
つまり、複数の遺言書がある場合は、作成日の前後及び内容が抵触するかどうかを確認し、抵触する部分については作成日の新しい遺言書が有効となります。
具体例
例えば、次のようなケースをみてみましょう。
①遺言書1:A不動産は長男甲に相続させる。B不動産は二男乙に相続させる。
②遺言書2:B不動産は長女丙に相続させる。
このような2通の遺言書がある場合、B不動産については、遺言書1と遺言書2の内容が抵触することから、遺言書2によって遺言書1のB不動産に関する部分が撤回されたものとみなされます。
その結果、遺言書1によって甲はA不動産を相続し、遺言書2によって丙はB不動産を相続することになります。
なお、遺言が有効であるためには、①遺言が法律の定める要件にしたがって作成されていること、②遺言書作成時に遺言者に遺言能力があったこと、が必要です。
そのため、遺言書が複数あったとしても、そのいずれかが無効の場合、内容の抵触は生じません。
例えば、先の例で、遺言書2が自筆証書遺言で、遺言書に作成日の記載がない場合や、遺言書2の作成時点で、遺言者が判断能力を喪失していたような場合は、遺言書2はそもそも無効であることから、遺言書1のみが有効な遺言となり、内容の抵触は生じないことになります。
参考条文
民法
(遺言の撤回)
第千二十二条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
第千二十四条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。